清水もつカレー総研事務局・清水ブランド大作戦事務局
2025年01月28日
はじめてのしょうてんがい
「第12回はじめてのしょうてんがい」が令和7(2025)年2月22日(土)23日(日)清水駅前銀座商店街、清水駅前商店街で行われます。

子どもたちがリアル店舗でおしごと体験ができます。
また、もらったお給料(疑似通貨)でお店で買い物もできます。

一年生から三年生はおつかいもあります。
まあるのホームページ はじめてのしょうてんがい ↓
https://maaru-ct.jp/news/217858/

子どもたちがリアル店舗でおしごと体験ができます。
また、もらったお給料(疑似通貨)でお店で買い物もできます。

一年生から三年生はおつかいもあります。
まあるのホームページ はじめてのしょうてんがい ↓
https://maaru-ct.jp/news/217858/
2025年01月18日
武田の痕跡妙正堂(1)

村松本能寺、今福丹波守の屋敷門と伝えられる山門を入ると正面にあるのが妙正堂
妙正堂縁起にはこのように記されている
この妙正堂は、本能寺の鎮守である、「妙正大善神」を祀っている。
妙正大善神は、疱瘡(天然痘のこと)から子供を護り、寿命・身体の育成と器量円満の霊験がある。
この妙正大善神は、甲斐武田家の重臣にして峡南の雄、身延下山の領主穴山梅雪(1541~1582)の息女を神格化した善神と伝える。
梅雪の息女は天正3 (1575)年12月1日に疱瘡で早世するが、臨終に際して「我は疱瘡で苦しむ子供達を守護するであろう」と遺言し、爾来安産や子育ての神として信仰されている。
毎年4月3日は妙正大善神の縁日である。 法要に併せて古雛のお焚き上げ供養をしている。これは妙正大善神が、子供の守り神であることによる。
尚、この妙正堂には「妙見大菩薩」、「八幡大菩薩」の二神を併せ祀っている。
また「不二見の百年」にもこのような記述がある
妙正様は山門正面に祀られてあるが、戦前は子供の守り神、疱瘡を予防する神様として、四月三、四日のお祭りには赤飯を炊いておにぎりにして配ったので子供連れの参拝者で賑わったそうです。
また近所の檀家の女性によれば、昔近所のおばあさんたちがこの妙正堂に集まって時を過ごしていたとのことでした。安産子育てと親しまれていたことがうかがわれます。
穴山梅雪(信君のぶただ)と本能寺の縁はよくわからないそうですが、江尻城代の時代に江尻城と久能山城を結ぶ久能街道にあるこの日蓮宗のお寺に立ち寄ることは十分考えられます。
梅雪は家康の調略により織田方となりましたが、その会見が行われたのが上原子安地蔵堂といわれ、旧東海道に残されています。
武田信玄、穴山梅雪とその娘(妙正さま)、身延山にまつわる伝承は次回
2025年01月09日
武田の痕跡本能寺

清水区村松の東光山本能寺
鎌倉時代の創建であり、正受院日東上人の開山で、同じく村松の日蓮宗本山海長寺の末寺である。
日東上人は駿河池田の本覚寺の9世貫首であり、本覚寺は日蓮上人が臨終のとき呼び寄せ後を託した六老僧の一人、日持上人の弟子日位上人(中老僧)が開山したお寺です。
さてその山門は、武田二十四将の一人、今福丹波守の屋敷門と伝えられている。
蟇股には今福家の家紋「剣酢漿草(けんかたばみ)」が彫られている。
でその今福丹波守友清(浄関斎)とはどのような武将であったか。
武田信玄が駿河侵攻の際、久能城の城代とした。
長男虎孝(昌守)、次男昌和、三男昌常。
のち諏訪原城に移るが、諏訪原城の戦い(1575年8月)で戦死、諏訪原城址には討死の碑があるが、一説には1581年病死とある。
三人の息子は久能城に逃げ帰ったとの説があるが、次男昌和は諏訪高島城城代で、1582年高遠城の戦で討死とある。
また久能城攻めで、長男虎孝は戦死とあるが逃亡し、家康を追い詰めて果たせず長男善十郎と自刃とあるのが、のちの海長寺の椿譚につながるのであろうか。
三男昌常は降伏し、家康に仕えた。

甲州武田軍団二十四将軍之一人 今福丹波守子孫家と石柱に彫られた山門のある家が存在する。
「丹波屋敷」と云われている今福丹波守の屋敷は、現在の海長寺の北側を境にして、久能街道を北へ、村松中組の「ホウトウさん」と云う坂を下り、幸町の境までが屋敷だったそうです。(不二見の百年 第9章昔話について 羽衣橋と丹波屋敷と其の賑わい)

今でいう、ポプラ並木通りからアジサイ通りにわたる、広大な屋敷が江戸時代から、いつごろまであったのであろうか。
黄色い線で囲んで想像してみた。
2025年01月04日
武田の痕跡甲州廻米置場
甲州廻米置場跡の碑が港橋バス停すぐそばにあるので、甲州の米置場があったことをご存じの方は多いと思います。
読みずらい碑文
「巴川東岸は向島といわれていた地で、こあたり520メートルは徳川時代に甲州から江戸へ送る年貢米を富士川船で岩淵岸につけ蒲原浜から清水港に廻送して千石船に積み込んだ場所であり寛保元年(1743)から明治5年(1872)まで存続した以降も北隅に水揚稲荷がまつられてある。清水市1950?」

もともとこの向島といわれていた土地は現在の島崎町、相生町、万世町あたりのことを云い、その先に寄州(よすー土砂が波風や水流によってできた州)ができ、向島の出来島と呼ばれたのがこの港町あたりだそうです。
三保半島を形作った土砂は三保半島を越えて堆積し、先の向島より北の横砂、真砂町という地名の通り清水の海岸線を形作っていった。
この土地に富士山宝永の大噴火があった年、甲斐甲府15万石藩主柳沢吉保の意を受けここに甲州廻米置場ができたのが始まりです。
鰍沢河岸(甲府代官所)、青柳河岸(石川代官所)、黒沢河岸(石和代官所)から発送された品物は富士川を南下し岩渕で中継、蒲原まで陸送、清水湊まで回送され、この廻米置場に集められ、千石船で江戸へ送られました。
しかし明治維新を迎え、上記河岸の既得権を廃し、また租税を年貢米から金納にし廻米輸送は禁止された。山梨県はまた、塩を生産地で直接仕入れ、陸路を使った輸送にしたため、富士川舟運は衰退し、やがて鉄路や陸路輸送に代わっていった。
廃藩置県後の明治6年、静岡県が民間に払い下げようとしたが、山梨県が歴史的経緯から所有権を主張しその結果山梨県有地となった。
都市計画等で縮小したとはいえ、現在も624坪2060平方メートルが山梨県の土地として残っている。
今もこの土地の北の隅には、水揚稲荷がひっそりと祀られている。

読みずらい碑文
「巴川東岸は向島といわれていた地で、こあたり520メートルは徳川時代に甲州から江戸へ送る年貢米を富士川船で岩淵岸につけ蒲原浜から清水港に廻送して千石船に積み込んだ場所であり寛保元年(1743)から明治5年(1872)まで存続した以降も北隅に水揚稲荷がまつられてある。清水市1950?」

もともとこの向島といわれていた土地は現在の島崎町、相生町、万世町あたりのことを云い、その先に寄州(よすー土砂が波風や水流によってできた州)ができ、向島の出来島と呼ばれたのがこの港町あたりだそうです。
三保半島を形作った土砂は三保半島を越えて堆積し、先の向島より北の横砂、真砂町という地名の通り清水の海岸線を形作っていった。
この土地に富士山宝永の大噴火があった年、甲斐甲府15万石藩主柳沢吉保の意を受けここに甲州廻米置場ができたのが始まりです。
鰍沢河岸(甲府代官所)、青柳河岸(石川代官所)、黒沢河岸(石和代官所)から発送された品物は富士川を南下し岩渕で中継、蒲原まで陸送、清水湊まで回送され、この廻米置場に集められ、千石船で江戸へ送られました。
しかし明治維新を迎え、上記河岸の既得権を廃し、また租税を年貢米から金納にし廻米輸送は禁止された。山梨県はまた、塩を生産地で直接仕入れ、陸路を使った輸送にしたため、富士川舟運は衰退し、やがて鉄路や陸路輸送に代わっていった。
廃藩置県後の明治6年、静岡県が民間に払い下げようとしたが、山梨県が歴史的経緯から所有権を主張しその結果山梨県有地となった。
都市計画等で縮小したとはいえ、現在も624坪2060平方メートルが山梨県の土地として残っている。
今もこの土地の北の隅には、水揚稲荷がひっそりと祀られている。

2024年12月28日
武田の痕跡東明院
江尻城の遺構はないといわれるが、江尻城の裏門とされるのがこの東明院の山門です。
関ケ原の戦いに勝利したことにより存在理由がなくなったのか、家康により廃城となる際(慶長六年1601)この東明院に下賜されたものだといわれています。
ただその後の災害により消失、江戸時代後期に原型に復元されたものが現在の山門であり、門扉に残された南蛮鉄の武田菱の金具のみが400年前(1601)当時のものとなります。

山門には二基の鯱瓦が据えられ、寺門というより城門であったことがわかります。

南蛮鉄の武田菱


武田支配の江尻城時代の城代穴山梅雪は、この寺の和尚の徳を慕って梵鐘を寄進したと伝えられます。
しかしご覧のように、お寺の紋は、丸に二つ引き、これは今川家の家紋で今川ゆかりのお寺と思われます。
「御所(足利将軍家)が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」とまでいわれた名門です。
ご住職に尋ねると、武田もお寺は大切にしたとのことでした。
余談ですが、本堂の横には井戸があり現在も使われていて、2022年の台風15号で清水が4日間断水になったとき、井戸水を提供し近所の方に喜ばれたそうです。入江町のこの地区が水が豊富ということは知りませんでしたが、水を大量に使う紺屋が目の前の旧東海道沿いにありました。名前が木戸紺屋。江尻宿の西の木戸がここにあったゆえの屋号でした。
関ケ原の戦いに勝利したことにより存在理由がなくなったのか、家康により廃城となる際(慶長六年1601)この東明院に下賜されたものだといわれています。
ただその後の災害により消失、江戸時代後期に原型に復元されたものが現在の山門であり、門扉に残された南蛮鉄の武田菱の金具のみが400年前(1601)当時のものとなります。

山門には二基の鯱瓦が据えられ、寺門というより城門であったことがわかります。

南蛮鉄の武田菱


武田支配の江尻城時代の城代穴山梅雪は、この寺の和尚の徳を慕って梵鐘を寄進したと伝えられます。
しかしご覧のように、お寺の紋は、丸に二つ引き、これは今川家の家紋で今川ゆかりのお寺と思われます。
「御所(足利将軍家)が絶えれば吉良が継ぎ、吉良が絶えれば今川が継ぐ」とまでいわれた名門です。
ご住職に尋ねると、武田もお寺は大切にしたとのことでした。
余談ですが、本堂の横には井戸があり現在も使われていて、2022年の台風15号で清水が4日間断水になったとき、井戸水を提供し近所の方に喜ばれたそうです。入江町のこの地区が水が豊富ということは知りませんでしたが、水を大量に使う紺屋が目の前の旧東海道沿いにありました。名前が木戸紺屋。江尻宿の西の木戸がここにあったゆえの屋号でした。
2024年12月24日
武田の痕跡江尻城
戦国時代駿河を治めていた今川義元が、永禄3年(1560)尾張の桶狭間で織田信長の奇襲にあい戦死した後、永禄11年(1568)12月甲斐の国の武田信玄は駿河に攻め入りこの地を占領しました。
この時信玄はサクラエビで名高い由比、歌川広重の東海道五十三次で有名な富士山の絶景の地、薩埵峠に布陣、これに対して今川氏真はこれまた有名な清見の関、朝鮮通信使の寄宿場所、家康手習いの間もある清見寺に布陣したが、内通者もあり総崩れとなって信玄は、翌13日今川館を焼き払い、氏真は掛川城へ逃れた。しかしこのとき追撃しなかった、できなかった。というのは早くも北条勢先鋒が蒲原城に入ったためでした。
永禄13年(1570)信玄は東の北条氏、西の徳川氏に対抗するため、蛇行する巴川を利用して、山本勘助に城取りの極意を伝授された馬場美濃守信春の縄張りによりここに江尻城を築きました。城代には武田四天王、赤備えでおそれられた猛将山県昌景を置いた。今も清水には美濃守屋敷があったところが美濃輪町という町名として残っています。最初の城代、山県昌景は、というと長篠の戦い(1575)で戦死。
山県昌景の死後、穴山梅雪が城代となりましたが、1575年の長篠の戦が5月、6月光明寺城(浜松市天竜区)、8月諏訪原城(1573年勝頼築く)、12月二俣城が家康の手に落ちました。また1577年には高天神城も家康が攻撃を始めました。このような状況のなか、
天正6年(1578)、城を大改築して高層高さ30mの楼閣を建て「観国楼」と名付け、江尻を城下町とする本格的な城となりましたが、天正10年(1582)3月、西から攻めてきた徳川家康に降伏して江尻城を明け渡しました。その後家康が江戸に移るとともに、慶長六年(1601)城ができてから三十二年を経て廃城となりました。(下線は江尻まちづくり推進委員会の看板より引用)
さて、指定文化財なし、遺構なしといわれる江尻城址ですが、わずかながらその痕跡を見ることができます。
というか、現地調査で私なりに発見したので報告します。それは堀の跡ですが、静岡古城研究会の「中世城郭縄張図集成」から推測しその痕跡がはっきり見ることができました。

偶然にも、前の敷地が更地になっていたため、堀跡が見て取れました。写真中央の建物は明らかに左右の家より低く沈んだ場所に立っています。堀跡です。

また堀跡と思われるところをのぞいてみると、写真ではよくわかりずらいのですが、先の自動車がある位置と自転車の位置は明らかに下がっており、また撮影場所は高くなっています。堀跡と推測されます。

これは魚町稲荷神社の巴川側の際とともに堀跡ととして知られている小芝神社南側の路地です。

その小路を抜けた先、道路を横断した先は、このように曲がった道があり突き当りになっています。この変な形状も堀跡の続きと推測されます。
推測といっても古城研究会の縄張図にははっきり堀跡として示されています。
というわけで、ブラタモリよろしく失われてしまった、忘れ去られてしまったといわれる江尻城址もわずかながら戦国の痕跡を残しているのが見て取れました。
この時信玄はサクラエビで名高い由比、歌川広重の東海道五十三次で有名な富士山の絶景の地、薩埵峠に布陣、これに対して今川氏真はこれまた有名な清見の関、朝鮮通信使の寄宿場所、家康手習いの間もある清見寺に布陣したが、内通者もあり総崩れとなって信玄は、翌13日今川館を焼き払い、氏真は掛川城へ逃れた。しかしこのとき追撃しなかった、できなかった。というのは早くも北条勢先鋒が蒲原城に入ったためでした。
永禄13年(1570)信玄は東の北条氏、西の徳川氏に対抗するため、蛇行する巴川を利用して、山本勘助に城取りの極意を伝授された馬場美濃守信春の縄張りによりここに江尻城を築きました。城代には武田四天王、赤備えでおそれられた猛将山県昌景を置いた。今も清水には美濃守屋敷があったところが美濃輪町という町名として残っています。最初の城代、山県昌景は、というと長篠の戦い(1575)で戦死。
山県昌景の死後、穴山梅雪が城代となりましたが、1575年の長篠の戦が5月、6月光明寺城(浜松市天竜区)、8月諏訪原城(1573年勝頼築く)、12月二俣城が家康の手に落ちました。また1577年には高天神城も家康が攻撃を始めました。このような状況のなか、
天正6年(1578)、城を大改築して高層高さ30mの楼閣を建て「観国楼」と名付け、江尻を城下町とする本格的な城となりましたが、天正10年(1582)3月、西から攻めてきた徳川家康に降伏して江尻城を明け渡しました。その後家康が江戸に移るとともに、慶長六年(1601)城ができてから三十二年を経て廃城となりました。(下線は江尻まちづくり推進委員会の看板より引用)
さて、指定文化財なし、遺構なしといわれる江尻城址ですが、わずかながらその痕跡を見ることができます。
というか、現地調査で私なりに発見したので報告します。それは堀の跡ですが、静岡古城研究会の「中世城郭縄張図集成」から推測しその痕跡がはっきり見ることができました。

偶然にも、前の敷地が更地になっていたため、堀跡が見て取れました。写真中央の建物は明らかに左右の家より低く沈んだ場所に立っています。堀跡です。

また堀跡と思われるところをのぞいてみると、写真ではよくわかりずらいのですが、先の自動車がある位置と自転車の位置は明らかに下がっており、また撮影場所は高くなっています。堀跡と推測されます。

これは魚町稲荷神社の巴川側の際とともに堀跡ととして知られている小芝神社南側の路地です。

その小路を抜けた先、道路を横断した先は、このように曲がった道があり突き当りになっています。この変な形状も堀跡の続きと推測されます。
推測といっても古城研究会の縄張図にははっきり堀跡として示されています。
というわけで、ブラタモリよろしく失われてしまった、忘れ去られてしまったといわれる江尻城址もわずかながら戦国の痕跡を残しているのが見て取れました。
2024年12月07日
武田の痕跡@清水
戦国武田氏の清水における痕跡

~清水は今川でも徳川でもなく武田だ!戦国武田の痕跡を清水に訪ねる~
1568年から1582年にわたる戦国大名武田氏の駿河支配は清水を拠点に行われた。
その痕跡が清水には多く残されている。
しかしそのことは清水区民の口の端に上ることは少なく、次郎長さんには比べるべくもない。
このたび中部横断道の開通により、甲斐武田氏の国の人々との交流も格段に容易となり行き来が盛んになりつつある。清水の持つ自然、風土、産業などに加えて戦国時代の武田氏支配の清水の歴史を魅力の一つに加え、何より市民(区民)による歴史認識を深めることにより、清水の元気がでればいい。
1)江尻城址 1570年武田氏により築城馬場美濃守信春の縄張り 山県昌景、穴山信君城主。そこにある魚町稲荷は穴山梅雪(信君)が建立、またサッカー神社とも云われている
2)東明院 現存する武田菱の南蛮鉄製門扉は江尻城の山門だったと伝えられる
3)甲州廻米置き場
4)袋城 市街地化で消滅しているが、城のものとされる石がある。北条水軍に備えるため馬場美濃守が山本勘助流の縄張りにより築城 美濃輪町の地名が残っている。
5)本能寺 山門は武田武将の一人今福家の屋敷門 山門の内側にある蟇股に今福家家紋剣酢漿草ケンカタバミが彫刻されている。境内にある妙正堂は梅雪の息女を神格化した妙正大善神を祀る。臨終に際し我は疱瘡に苦しむ子供達を守護すると残した。
6)海長寺 武田の暗殺軍団今福丹波守主従七人の武士に襲われた家康がその影に隠れて難を逃れたという椿がある
7)杉原山虚空蔵堂 ついに家康を探し出すことができずこの地で自害した今福丹波守主従。村人がこの七人の悲運を哀れに思って「七代様」と呼んで供養した。
8)今福丹波守子孫の家と石柱に彫られている山門のある家
9)補陀落山楞厳院 武田家臣 清水湊船奉行 土屋豊前守貞綱が開基
10)穴山梅雪の墓 興津井上町霊泉寺 梅雪開基の寺
11)久能城 武田勝頼が1575年久能寺を村松妙音寺に移転させ築城
今後いくつかを紹介していきたい

~清水は今川でも徳川でもなく武田だ!戦国武田の痕跡を清水に訪ねる~
1568年から1582年にわたる戦国大名武田氏の駿河支配は清水を拠点に行われた。
その痕跡が清水には多く残されている。
しかしそのことは清水区民の口の端に上ることは少なく、次郎長さんには比べるべくもない。
このたび中部横断道の開通により、甲斐武田氏の国の人々との交流も格段に容易となり行き来が盛んになりつつある。清水の持つ自然、風土、産業などに加えて戦国時代の武田氏支配の清水の歴史を魅力の一つに加え、何より市民(区民)による歴史認識を深めることにより、清水の元気がでればいい。
1)江尻城址 1570年武田氏により築城馬場美濃守信春の縄張り 山県昌景、穴山信君城主。そこにある魚町稲荷は穴山梅雪(信君)が建立、またサッカー神社とも云われている
2)東明院 現存する武田菱の南蛮鉄製門扉は江尻城の山門だったと伝えられる
3)甲州廻米置き場
4)袋城 市街地化で消滅しているが、城のものとされる石がある。北条水軍に備えるため馬場美濃守が山本勘助流の縄張りにより築城 美濃輪町の地名が残っている。
5)本能寺 山門は武田武将の一人今福家の屋敷門 山門の内側にある蟇股に今福家家紋剣酢漿草ケンカタバミが彫刻されている。境内にある妙正堂は梅雪の息女を神格化した妙正大善神を祀る。臨終に際し我は疱瘡に苦しむ子供達を守護すると残した。
6)海長寺 武田の暗殺軍団今福丹波守主従七人の武士に襲われた家康がその影に隠れて難を逃れたという椿がある
7)杉原山虚空蔵堂 ついに家康を探し出すことができずこの地で自害した今福丹波守主従。村人がこの七人の悲運を哀れに思って「七代様」と呼んで供養した。
8)今福丹波守子孫の家と石柱に彫られている山門のある家
9)補陀落山楞厳院 武田家臣 清水湊船奉行 土屋豊前守貞綱が開基
10)穴山梅雪の墓 興津井上町霊泉寺 梅雪開基の寺
11)久能城 武田勝頼が1575年久能寺を村松妙音寺に移転させ築城
今後いくつかを紹介していきたい
2024年05月04日
みどりの日とまち
林野庁のホームページに、森林の有する多面的機能というページがあり次のような機能が紹介されている。
1.生物多様性保全
遺伝子保全・生物種保全(植物種保全、動物種保全:鳥獣保護、菌類保全)・生態系保全(河川生態系保全、沿岸生態系保全:魚つき)
2.地球環境保全
地球温暖化の緩和(二酸化炭素吸収、化石燃料代替エネルギー)・地球気候システムの安定化
3.土砂災害防止機能/土壌保全機能
表面浸食防止・表層崩壊防止・その他の土砂災害防止(落石防止、土砂流発生防止:停止促進、飛砂防止・土砂流出防止・土壌保全(森林の生産力維持)・その他の自然災害防止機能(雪崩防止、防風、防雪、防潮など)
4.水源涵養機能
洪水緩和・水資源貯留・水量調節・水質浄化
5.快適環境形成機能
気候緩和(夏の気温低下と冬の気温上昇)、木陰・大気浄化(塵埃吸着、汚染物質吸着)・快適生活環境形成(騒音防止、アメニティ)
6.保健・レクリエーション機能
療養(リハビリテーション)・保養(休養:休息、リフレッシュ、散策、森林浴)・レクリエーション(行楽、スポーツ、つり)
7.文化機能
景観(ランドスケープ)風致・学習:教育(生産、労働体験の場、自然認識:自然とのふれあいの場)・芸術・宗教:祭礼・伝統文化・地域の多様性の維持(風土形成)
8.物質生産機能
木材(燃料材、建築材、木製品原料、パルプ原料)・食糧・肥料・飼料・薬品その他の工業原料・緑化材料・観賞用植物・工芸材料
森林は日本の総面積の68.2%を占めるにもかかわらず、日本は世界でも有数の木材輸入国であり、木材の自給率は20%を切っている。木材の生産ということで考えたら、日本の森林はグローバル化の中で競争力は低下し、雇用人口は減り、高齢化がすすみ存在が危ぶまれている。しかし森林はなくてはならない機能を持っているのだ。
では商店街はどうだろうか。カメラ雑誌を眺めていたら「商店街が壊される」として、マンション建設のためアーケードが取り払われる写真があり記事にはこう書かれていた。
「一体商店街は今や何のために存在するのだろう、誰かの歌の歌詞の中にあったように、面白くもなくつまらなくもない場所」と。
ものの売り買いという機能は著しく低下してしまったが、森が多面的機能を持っているように商店街やまちは多くの社会的機能を持ち社会的役割を果たしてきたのではないか。
1.コミュニティ(地域社会・共同体)保全機能
農業社会から工業社会への変化の中で、人々がふるさとを離れ、地域においても、住居から離れて会社勤めをするようになり、地域社会での人々の結びつきが薄れコミュニティの崩壊がいわれて久しいが、中心部で暮らしと仕事が一体となっている商店街は、地域のコミュニティの核となっている。
2.地域文化(暮らし・祭り・伝統・習俗・考え方・習慣・気質)保全機能
地域の「らしさ」を表していて、よそからの人の目に触れやすく、またそのアイデンティティに誇りを持って暮らす人々によって地域らしさは守られる
3.安全・治安・防犯・防災
匿名性があり、流動性の高い地域に犯罪が起こりやすい、つまり郊外大型ショッピングセンターにはどこの誰だかわからない人たちが集まり、自動車でどこからでも集まり去っていく。昔ながらの商店街では、ある程度顔が見え、人の目が犯罪を抑制している。
4.教育
「商店街では様々な商店が奥でモノを作り、常に働く人が目に見えていたし、働く人同士、例えばカマボコ店に板や包装紙の業者が出入りし、社会が形成していることが肌でわかった。農村もそれぞれ助け合って生活していた」「そうした環境で育てば自然に社会で生きる力を身につけられるが、郊外は寝て消費するだけ。労働や生産機能がない。フリーターや二ートも郊外から生まれる」三浦展氏
5.地域文化のテーマパーク
ちびまる子や次郎長に見られる、清水人の気質・心意気・優しさ・面白さを感じられる場所としての中心街。地域人の生息地、簡単にふれ合うことのできる場所
6.保健機能(リハビリテーション機能・癒し機能)
7.地域経済循環機能
8.環境保全機能
9.福祉機能
10.まちの顔・地域アイデンティティ
11.まちの広場・居間・出会いの場

紙面がなく以前のインフォメーションにもまちのもつ機能について記述したので重複はさけるが、このような機能を市民、行政に理解してもらい、商店街は半公共施設であり、社会を維持するための重要な装置であるということを訴えていきたい。と同時に個店が営業し続けることが、まちを守ることになることを私たちは認識し続けるべきと思う。何をしたらいいか考えよう。
2007年10月記
1.生物多様性保全
遺伝子保全・生物種保全(植物種保全、動物種保全:鳥獣保護、菌類保全)・生態系保全(河川生態系保全、沿岸生態系保全:魚つき)
2.地球環境保全
地球温暖化の緩和(二酸化炭素吸収、化石燃料代替エネルギー)・地球気候システムの安定化
3.土砂災害防止機能/土壌保全機能
表面浸食防止・表層崩壊防止・その他の土砂災害防止(落石防止、土砂流発生防止:停止促進、飛砂防止・土砂流出防止・土壌保全(森林の生産力維持)・その他の自然災害防止機能(雪崩防止、防風、防雪、防潮など)
4.水源涵養機能
洪水緩和・水資源貯留・水量調節・水質浄化
5.快適環境形成機能
気候緩和(夏の気温低下と冬の気温上昇)、木陰・大気浄化(塵埃吸着、汚染物質吸着)・快適生活環境形成(騒音防止、アメニティ)
6.保健・レクリエーション機能
療養(リハビリテーション)・保養(休養:休息、リフレッシュ、散策、森林浴)・レクリエーション(行楽、スポーツ、つり)
7.文化機能
景観(ランドスケープ)風致・学習:教育(生産、労働体験の場、自然認識:自然とのふれあいの場)・芸術・宗教:祭礼・伝統文化・地域の多様性の維持(風土形成)
8.物質生産機能
木材(燃料材、建築材、木製品原料、パルプ原料)・食糧・肥料・飼料・薬品その他の工業原料・緑化材料・観賞用植物・工芸材料
森林は日本の総面積の68.2%を占めるにもかかわらず、日本は世界でも有数の木材輸入国であり、木材の自給率は20%を切っている。木材の生産ということで考えたら、日本の森林はグローバル化の中で競争力は低下し、雇用人口は減り、高齢化がすすみ存在が危ぶまれている。しかし森林はなくてはならない機能を持っているのだ。
では商店街はどうだろうか。カメラ雑誌を眺めていたら「商店街が壊される」として、マンション建設のためアーケードが取り払われる写真があり記事にはこう書かれていた。
「一体商店街は今や何のために存在するのだろう、誰かの歌の歌詞の中にあったように、面白くもなくつまらなくもない場所」と。
ものの売り買いという機能は著しく低下してしまったが、森が多面的機能を持っているように商店街やまちは多くの社会的機能を持ち社会的役割を果たしてきたのではないか。
1.コミュニティ(地域社会・共同体)保全機能
農業社会から工業社会への変化の中で、人々がふるさとを離れ、地域においても、住居から離れて会社勤めをするようになり、地域社会での人々の結びつきが薄れコミュニティの崩壊がいわれて久しいが、中心部で暮らしと仕事が一体となっている商店街は、地域のコミュニティの核となっている。
2.地域文化(暮らし・祭り・伝統・習俗・考え方・習慣・気質)保全機能
地域の「らしさ」を表していて、よそからの人の目に触れやすく、またそのアイデンティティに誇りを持って暮らす人々によって地域らしさは守られる
3.安全・治安・防犯・防災
匿名性があり、流動性の高い地域に犯罪が起こりやすい、つまり郊外大型ショッピングセンターにはどこの誰だかわからない人たちが集まり、自動車でどこからでも集まり去っていく。昔ながらの商店街では、ある程度顔が見え、人の目が犯罪を抑制している。
4.教育
「商店街では様々な商店が奥でモノを作り、常に働く人が目に見えていたし、働く人同士、例えばカマボコ店に板や包装紙の業者が出入りし、社会が形成していることが肌でわかった。農村もそれぞれ助け合って生活していた」「そうした環境で育てば自然に社会で生きる力を身につけられるが、郊外は寝て消費するだけ。労働や生産機能がない。フリーターや二ートも郊外から生まれる」三浦展氏
5.地域文化のテーマパーク
ちびまる子や次郎長に見られる、清水人の気質・心意気・優しさ・面白さを感じられる場所としての中心街。地域人の生息地、簡単にふれ合うことのできる場所
6.保健機能(リハビリテーション機能・癒し機能)
7.地域経済循環機能
8.環境保全機能
9.福祉機能
10.まちの顔・地域アイデンティティ
11.まちの広場・居間・出会いの場
紙面がなく以前のインフォメーションにもまちのもつ機能について記述したので重複はさけるが、このような機能を市民、行政に理解してもらい、商店街は半公共施設であり、社会を維持するための重要な装置であるということを訴えていきたい。と同時に個店が営業し続けることが、まちを守ることになることを私たちは認識し続けるべきと思う。何をしたらいいか考えよう。
2007年10月記
2024年03月16日
2024年01月11日
はじめてのしょうてんがい開催
はじめてのしょうてんがいでは、コミュニティの核として多くの役割を担ってきた地域商店街において、子どもたちがより多くの大人と出会い、仕事を体験する機会をもつことで社会への関わりを深め、社会性をはぐくむことを目的としてきました。
「安心・安全」な場としての商店街が培ってきた「人との豊かなつながり」は、次世代へつなげるべきものだと信じ、11回目となるはじめてのしょうてんがいを開催します。
また商店街のみならず、地域のNPOや仕事体験を通じ社会・経済の仕組みや地域産業を学ぶ施設である「静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る」と連携し、地域が一体となり、子どもたちの成長を応援することを目的とします。
今年も2月17日(土)・18日(日)に、「はじめてのしょうてんがい」を開催する運びとなりました。
「第11回はじめてのしょうてんがい」につきまして、募集を開始いたしました。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
https://maaru-ct.jp/news/189434/
プログラムご応募はこちらから
2月17日(土)おつかい編
▶https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc9aH3z.../viewform
2月17日(土)おしごと編
▶https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfzVVlGTeCmbb.../viewform
2月18日(日)おつかい編
▶https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeeetohAOFykB.../viewform
2月18日(日)おしごと編
▶https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfSiNwXvpKVb3.../viewform
2023年11月23日
A級ディンギー for SALE
大学時代乗ってたヨット、A級ディンギー知り合いの艇を引っ張り出した。
オーナーが手放すことにしたからだ。
前々世紀設計のもう2度と手にすることができない芸術品。
一つ一つ思い出しながら艤装した。
思い出のいっぱい詰まった船だ。


65万円で売り出しています。
二度と手に入らない逸品 オーナーは芸術品だと行っています。
オーナーが手放すことにしたからだ。
前々世紀設計のもう2度と手にすることができない芸術品。
一つ一つ思い出しながら艤装した。
思い出のいっぱい詰まった船だ。



65万円で売り出しています。
二度と手に入らない逸品 オーナーは芸術品だと行っています。
2023年01月10日
はじめてのしょうてんがい
はじめてのしょうてんがいでは、コミュニティの核として多くの役割を担ってきた地域商店街において、子どもたちがより多くの大人と出会い、仕事を体験する機会をもつことで社会への関わりを深め、社会性をはぐくむことを目的として開催します。
今回は10回目となります。
詳しくはま・あ・るのお知らせをご覧ください
https://maaru-ct.jp/news/157455/
2022年05月03日
ポートサイドジャズ2022

第18回ポートサイドジャズinしみず
5月15日(日)午前10時~午後8時
エスパルスドリームプラザ 海側デッキ
入場無料
コロナ対策のため入場制限やマスク着用・検温などにご協力ください
Posted by クールなお at
09:40
│Comments(0)
2022年03月07日
次郎長の生きざま
「侠客という次郎長の生きざまを知る」
侠客とは「強きをくじき、弱きを助ける」を生き方とした。
そのためには時に法を越えた。
この生き方を貫いたのが次郎長であった。
渡世人の修羅場から社会事業家としての功績が語られるが、その根本となり貫き通したのが任侠だった。
受けた恩は返す義理、人を想う人情。これらの生き方が物語として人々を惹きつけ、多くの英雄たちと引き合わせた。
単なる無法者ではなかった。
晩年は懐手で、子どもたちに菓子を分け与える好々爺であり、困っている人には自分の着物を質に入れても助けた。
地位も名誉も財も求めず、任侠を貫いた。
功績をほめたたえられても、次郎長は鼻で笑うに違いない。
「自分は人が喜ぶことをしたかっただけ、困っている人をほっておけなかった」こう言うだろう。
まことに清水らしいお人好しのひとだった。
これこそ漢(おとこ)のなかの漢一匹ではなかろうか。
侠客とは「強きをくじき、弱きを助ける」を生き方とした。
そのためには時に法を越えた。
この生き方を貫いたのが次郎長であった。
渡世人の修羅場から社会事業家としての功績が語られるが、その根本となり貫き通したのが任侠だった。
受けた恩は返す義理、人を想う人情。これらの生き方が物語として人々を惹きつけ、多くの英雄たちと引き合わせた。
単なる無法者ではなかった。
晩年は懐手で、子どもたちに菓子を分け与える好々爺であり、困っている人には自分の着物を質に入れても助けた。
地位も名誉も財も求めず、任侠を貫いた。
功績をほめたたえられても、次郎長は鼻で笑うに違いない。
「自分は人が喜ぶことをしたかっただけ、困っている人をほっておけなかった」こう言うだろう。
まことに清水らしいお人好しのひとだった。
これこそ漢(おとこ)のなかの漢一匹ではなかろうか。
2021年04月07日
ポートサイドジャズやります

第17回ポートサイドジャズinしみず
昨年はコロナ禍で中止になりましたが、今年は対策をしっかりやって開催します。
客席エリアないでは、マスクの着用、検温、アルコール消毒、飲食禁止、ソーシャルディスタンスなどのご協力をお願いします。
ストレスを感じそうですが、5月の青空のもと港でのジャズ、お出かけください。
天候の心配と県のステージが上がりましたが、予定通り16日行いました。
2020年05月13日
特別定額給付金on line
特別定額給付金申請受付が始まっているらしい。
オンラインなら自宅で申請、しかも早く給付が受けられる
ということでネット検索
ところが
パソコンからはICカードリーダーライターが必要ということで×
スマホはその数千円から1万円ほどする機器は要らないということだったが
マイナポータルAPというアプリのインストールが必要であり
わがスマホは対応していないということが判明×
オンライン申請は不可となった。
これってハードル高くない?
申請受付開始日5月11日(これも検索して初めて知った)の受付は3,800件
対象人数比は0.54%
対象世帯数比は1.2%
ICカードリーダーライターを持っている人
NFC機能のあるスマホ
これらの条件を満たさないと、オンライン申請はできない。
ただiPhone7以上ではできるらしいので、アップル好きの人はお早めにどうぞ。
オンラインなら自宅で申請、しかも早く給付が受けられる
ということでネット検索
ところが
パソコンからはICカードリーダーライターが必要ということで×
スマホはその数千円から1万円ほどする機器は要らないということだったが
マイナポータルAPというアプリのインストールが必要であり
わがスマホは対応していないということが判明×
オンライン申請は不可となった。
これってハードル高くない?
申請受付開始日5月11日(これも検索して初めて知った)の受付は3,800件
対象人数比は0.54%
対象世帯数比は1.2%
ICカードリーダーライターを持っている人
NFC機能のあるスマホ
これらの条件を満たさないと、オンライン申請はできない。
ただiPhone7以上ではできるらしいので、アップル好きの人はお早めにどうぞ。
Posted by クールなお at
09:38
│Comments(0)





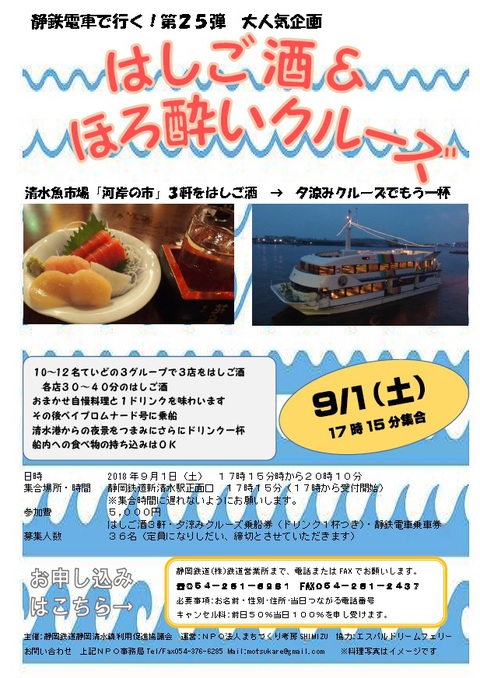
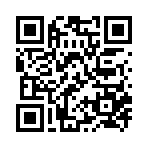

 Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved