清水もつカレー総研事務局・清水ブランド大作戦事務局
2009年12月07日
武田信玄と清水
久能寺観音道が有度山の根方をつたい久能寺(現鉄舟寺)にさしかかる少し手前に杉原山がある。
この麓にある、虚空蔵堂は武田信玄のいわれのあるお堂。
杉原山虚空蔵堂
このあたりは杉原山と言います。今から約五百年前に創立された本能寺、村松一丁目のたきぎ取りの山であり、当時は杉原山全体が同寺の飛び地境内でありました。現在、この仏堂の境内地は六十六平方㍍程であります。
戦国時代、甲斐の武田信玄がまだ世に出なかった徳川家康を攻め、窮地に陥れました。その時、家康を追いつめたのは信玄の家臣、今福丹波守主従七人であったといわれますが、ついに家康を探し出すことができず、御主君に申しわけないと、この地で無念の自害をしたと伝えられています。
後に村人達はこの七人の悲運を哀れに思って「七代様」と呼んで供養してきました。
七代様を虚空蔵菩薩としてお祭りするようになったのは、今から二百年余り昔の明和八年(1771年)本能寺第十八世遠寿院日問上人の時からであります。
昭和六十年二月 不二見地区まちづくり推進委員会 清水市立第四中学校郷土研究会
うーん、敵を探し出せなくて自害となると、いくつ命があっても足りないし、戦力の重大な損失であるなぁ、と思ったところ、武田信玄好き山梨県の盆地中央から気になって思わずふらふらっとここへやってきたという人のブログでは
今福丹波守虎孝は久能山城城代を父から引継ぎこの地域を治めますが、天正十年2月、徳川軍に攻められ城を脱出。この地で子である善十郎とともに自刃した、とあります。案内板では武田信玄を絡め、ちょっとかわった説明になっています。
とありました。
とにかくこの地で、武田信玄の武将が悲運の死を遂げ、それを村人が供養してきて、現在でもお線香やお花が供えられ、お詣りする人があることが分かる。
そしてお堂の中にはこのような愛らしい木彫のお地蔵様がいる。
この地の人は、なにか昔からの言い伝えを伝承している、心優しい人たちという思いを持った。
すぐ近くには「言い成り地蔵」があり、そちらへも多くの人がお詣りしていると聞く。
そして、この杉原山から海へまっすぐにのびる「ポプラ並木通り」を、本能寺あたりまで下った左側に、今福丹波守子孫の家がある。
ふつうの民家のようだが、武家に許された立派な門がある。
そして先ほどの本能寺にも、「山門は戦国時代庵原郡一帯を領有した甲州武田軍団の武将今福家の母屋の門という」説明文があり、
また入江町の東明院の南蛮鉄製門扉にも武田菱があり、それは武田家の重臣穴山梅雪が城主だった江尻城のものだったという。
こうしてみると、武田信玄との縁が深い「清水」が見えてきました。
Posted by クールなお at 19:00│Comments(2)
│our town
この記事へのコメント
良いレポートを拝読。
私もチャリンコで巡ってみたいと思います。
文化と歴史を伝えるのにブログも使えますな。
昔からある寺には隠れた歴史が残っているかもしれません。
なおさんのレポートをこれからも楽しみにしています。
私もチャリンコで巡ってみたいと思います。
文化と歴史を伝えるのにブログも使えますな。
昔からある寺には隠れた歴史が残っているかもしれません。
なおさんのレポートをこれからも楽しみにしています。
Posted by スプリング・フィールド(S・F) at 2009年12月08日 14:17
>S・Fさん
戦国時代は、武田の支配がどれだけあったものか、定かではないけど、これだけ遺構があるということは、結構な時間あったのかもしれない。
志みづ道のほろ酔いツアーも面白かったですよ。
歴史と利き酒、S・Fさんにぴったりだと思うけど、今度は参加してください。
戦国時代は、武田の支配がどれだけあったものか、定かではないけど、これだけ遺構があるということは、結構な時間あったのかもしれない。
志みづ道のほろ酔いツアーも面白かったですよ。
歴史と利き酒、S・Fさんにぴったりだと思うけど、今度は参加してください。
Posted by クールなお at 2009年12月09日 12:15
at 2009年12月09日 12:15
 at 2009年12月09日 12:15
at 2009年12月09日 12:15







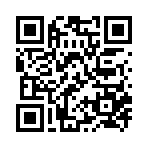

 Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved