清水もつカレー総研事務局・清水ブランド大作戦事務局
2008年10月20日
如意輪観世音菩薩
清見寺にあるという「瑞雲院」にある秘仏が60年に一度のお開帳があると新聞で知る。何せ、60年だから、ワタクシの生まれる前、昭和23(1948)年子の年に開帳して以来、そして次は年号はいざ知らず西暦2068年!ということになる。
なんというスケールの大きさ!悠久の宇宙を思わせるサイクルの催しではないだろうか。
ということで、自転車で出発!(なんというスローな交通手段)
東海道も、西久保に入り袖師、横砂となると、それ以前の辻(江尻宿の東の木戸があった)とはがらりと雰囲気が違う。

このあたりの伝統的な家、母屋の屋根と、玄関と縁側の屋根が二重になっている。
以前は、このような家が建ち並び、このあたりの町並みも、飛騨高山や妻籠・馬籠のようだったと思わせる。

側面を見るとその構造が良くわかる。
なぜこのような構造が、この地にあったのかわからない。
ある時代の建築工法で、ここに適していたのかもしれない。

新築し直すにしても、この家のように伝統的な形式を継承しているお宅もある。
しかしほとんどの新しい家は、今風の家になっている。
すぐれた建築家の何人かは、まずその地の地霊とでもいうべきもの、場所の持つDNAを見るというか、感じ、それを取り入れ設計するという。
そのような家並みが残っている地が美しいといわれているのかもしれない。
 で、波多打川を越えて興津清見寺にはいると各家には提灯が掲げられていて、
で、波多打川を越えて興津清見寺にはいると各家には提灯が掲げられていて、
がらっと変わり、まつりの雰囲気だ。

15分ほどで、清見寺に到着。坐魚荘でも何かイベントがあり、(時間切れで確かめることあたわず)、この駐車場でも町娘の着物姿で、茶屋を出している。派手なパフォーマンスはなさそうだが、今日はお祭だ!という雰囲気がまちの空気を占めている


登っていくと、平成20年のご開帳だ!という看板が、そして境内はお祭ムード一杯で、テントのしたでは氏子?檀家?が一杯やっているし、飲み物やらも売っている。

おりしも、演芸と言うことで桂歌助師匠の落語が始まるはじまる、
本堂に一杯の人で、これは菩薩さまへのご参拝はかなわぬなと、とりあえず一席を拝聴。
生で、真打ちの落語を聞くという機会も記憶にないので、これも何十年に一度のありがたさと思い聞くが、楽しい。
肝心の如意輪観世音菩薩さまは、本堂隣のお堂におわしました。

秘仏ということで、もちろん写真撮影禁止。
お姿は、半跏普趺坐像で片手をほほにつけている。
無事参拝も終わり、帰路につくと「清見神社」ご祭礼の門灯が!


清見寺は有名だが、清見神社は知らなかった。
ご祭礼の時でもあるので、ご参拝に伺うことにする。
知り合いに神社フェチとでもいう人がいて、小さな名もない神社が好きで、
その地の氏神さま、守り神、その地の聖地、の空気がすきといっていた。


小路?参道を行くと、東海道線が現れる。踏切はないのでいわゆる「赤道(あかみち)」を渡る。鳥居につづくのが急勾配の180段の石段。
興津川から富士川の間、海岸に迫る断崖(ちょっとオーバーか)の地は、
稲作が平地にひろがる以前の狩猟採集の時代には、豊かなところだったのではないだろうか。
そして、海での漁の時目印になるのがこのような高台にある神社であり、自分の住まうところの守り神、氏神であり、海からの恵みの神に感謝する場所だったのだろう。
と勝手に考察するのである。


祭礼といっても全て終わっていてなにもなく、新調されたしめ縄ときれいに掃き清められた跡が残っているのみである。
しかし、清々しい場所であり、もっと人々の生活のなかに入ってもいいようだが、
生活のあり方が、第一次産業から三次産業へと変化してきた今では、
神様も存在が薄くなってしまった。
家に帰り、お土産をいただく。
創業明治30年の 潮屋 宮様まんじゅうと、
入江南町の栗田煎餅の焼き印いりおせんべい。
どちらもおいしゅうございました。
なんというスケールの大きさ!悠久の宇宙を思わせるサイクルの催しではないだろうか。
ということで、自転車で出発!(なんというスローな交通手段)
東海道も、西久保に入り袖師、横砂となると、それ以前の辻(江尻宿の東の木戸があった)とはがらりと雰囲気が違う。
このあたりの伝統的な家、母屋の屋根と、玄関と縁側の屋根が二重になっている。
以前は、このような家が建ち並び、このあたりの町並みも、飛騨高山や妻籠・馬籠のようだったと思わせる。
側面を見るとその構造が良くわかる。
なぜこのような構造が、この地にあったのかわからない。
ある時代の建築工法で、ここに適していたのかもしれない。
新築し直すにしても、この家のように伝統的な形式を継承しているお宅もある。
しかしほとんどの新しい家は、今風の家になっている。
すぐれた建築家の何人かは、まずその地の地霊とでもいうべきもの、場所の持つDNAを見るというか、感じ、それを取り入れ設計するという。
そのような家並みが残っている地が美しいといわれているのかもしれない。
がらっと変わり、まつりの雰囲気だ。
15分ほどで、清見寺に到着。坐魚荘でも何かイベントがあり、(時間切れで確かめることあたわず)、この駐車場でも町娘の着物姿で、茶屋を出している。派手なパフォーマンスはなさそうだが、今日はお祭だ!という雰囲気がまちの空気を占めている
登っていくと、平成20年のご開帳だ!という看板が、そして境内はお祭ムード一杯で、テントのしたでは氏子?檀家?が一杯やっているし、飲み物やらも売っている。
おりしも、演芸と言うことで桂歌助師匠の落語が始まるはじまる、
本堂に一杯の人で、これは菩薩さまへのご参拝はかなわぬなと、とりあえず一席を拝聴。
生で、真打ちの落語を聞くという機会も記憶にないので、これも何十年に一度のありがたさと思い聞くが、楽しい。
肝心の如意輪観世音菩薩さまは、本堂隣のお堂におわしました。
秘仏ということで、もちろん写真撮影禁止。
お姿は、半跏普趺坐像で片手をほほにつけている。
当山の観音様「如意輪観世音菩薩」は、805年(延暦年間)伝教大師「最澄」一刀三礼の作という。1356年(延文元年)足利尊氏はこの観音様を「清浄観」と称し、よく帰依し戦死者慰霊及び武運長久、一族安全を祈願されました。1357年尊氏は開基となり、佛満禅師を招き開山とし、ここを瑞雲庵と号した。観音さまはお堂中央の厨子に安置され、60年に一度のお開帳にあたり参拝参拝が許される秘仏とされています。(案内より)
無事参拝も終わり、帰路につくと「清見神社」ご祭礼の門灯が!
清見寺は有名だが、清見神社は知らなかった。
ご祭礼の時でもあるので、ご参拝に伺うことにする。
知り合いに神社フェチとでもいう人がいて、小さな名もない神社が好きで、
その地の氏神さま、守り神、その地の聖地、の空気がすきといっていた。
小路?参道を行くと、東海道線が現れる。踏切はないのでいわゆる「赤道(あかみち)」を渡る。鳥居につづくのが急勾配の180段の石段。
興津川から富士川の間、海岸に迫る断崖(ちょっとオーバーか)の地は、
稲作が平地にひろがる以前の狩猟採集の時代には、豊かなところだったのではないだろうか。
そして、海での漁の時目印になるのがこのような高台にある神社であり、自分の住まうところの守り神、氏神であり、海からの恵みの神に感謝する場所だったのだろう。
と勝手に考察するのである。
祭礼といっても全て終わっていてなにもなく、新調されたしめ縄ときれいに掃き清められた跡が残っているのみである。
しかし、清々しい場所であり、もっと人々の生活のなかに入ってもいいようだが、
生活のあり方が、第一次産業から三次産業へと変化してきた今では、
神様も存在が薄くなってしまった。
家に帰り、お土産をいただく。
創業明治30年の 潮屋 宮様まんじゅうと、
入江南町の栗田煎餅の焼き印いりおせんべい。
どちらもおいしゅうございました。


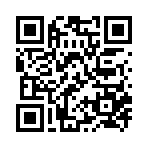

 Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/まちはみんなの宝箱 ALL Rights Reserved